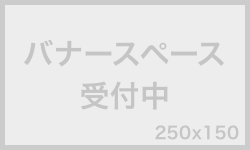オンラインの語学スクールは、一般的な学校や通学型の語学スクールと違い、講師のバリエーションが多いのが特徴です。
つまり、学歴や地域・資格・年齢・日本語能力・中国語教授能力、その他バラバラな属性の講師が集まっている、という傾向があります。
これはなぜかというと、スクールにより採用基準が異なり、一般的には門戸を広くしている場合が多いからと言えます。
自身にあった講師を自由に選べる仕組みは便利なものですが、なかなか相性の良い講師に出会えず、結局はオンラインでの学習を諦めてしまった、などという結果になってしまったら惜しいことです。
フリー制か担任制か?
まず、学習を開始する前に、レッスンの進め方には次の2つの方式がある* ということを念頭に入れておきましょう。
- フリー制(レッスンごとに自由に講師を選べる方式)
- 担任制(学習目的によって講師を固定する方式・講師の選択をスクールに一任できる場合もある)
*スクールによってはどちらか一方しかない場合もあります。
講師を選ぶ前に、どちらの方式で学習する方が目的にかなっているのか、というところから出発する必要があります。
もし、あなたが、ある程度計画的に学習して行きたいと思っている場合、固定の講師(担任制)を選び、カリキュラムを進める方が良いでしょう。
例えば、
- 次回のHSK◯級、中検◯級に合格したい
- 海外出張・旅行までに基礎を習得したい
- 早急にビジネス会話をマスターする必要がある
…などというような目的が該当します
こうした場合、カリキュラムを組むことができる経験豊富な講師を選択、あるいはリクエストし、担任として指導を受けるのがベストと言えます。
もちろん、スクール自体も担任制を謳っている所から選ぶのが基本になります。
しかし、もしあなたが特に必要に迫られているのではなく、趣味として中国語を学んでいるのであれば、必ずしも担任制にこだわる必要はないと思います。
何人かの講師のレッスンをランダムで受講し、フリートークで会話力をつけている受講者もいます。
ただ、もしあなたが入門者、あるいは初心者の場合、この方式だと内容が散漫になってしまい、なかなかコツを飲み込むことが難しいと思われます。
入門者・初心者の方は、なるべく早く最適な講師を見つけ、ある程度の期間じっくりとその講師に付いて学んでいくことをお勧めします。
もちろん、時間や費用に余裕のある方は、両者を併用していくのも良いと思います!
入門者・初心者に最適な講師
上述の通り、入門者の方は「担任制」のスクールを選ぶのが正解と言えます。
では、どのような講師が適しているのでしょうか?
実のところ、教える方としては入門者や初心者に対して教える方が難易度が高く、専門的な知識や経験が必要になります。
たとえば、あなたは日本語の基礎、「てにをは」などの助詞の知識や、活用や受け身や完了etcの文法知識を正しく教えることが出来ますか?
おそらく、教授法の知識がなければ、我々が自然に身に付けてきた母語の解釈を他人にすることはとても難しいでしょう。
さらに、ピンインの学習はもちろん、一音一音の発音をしっかり身に付けないと先に進むことが出来ません。
というわけで、入門・初心者には、
- 指導経験豊富な講師
- 発音が標準的な講師
- 中国語指導の資格(对外汉语教师资格证)を持っている講師
- 日本語が堪能な講師
をお勧めします。このような講師は、レッスン単価が高めの傾向がありますが、この時期での講師選びのミスは致命的ですので、費用を惜しむべきではないと思います。
会話力向上に最適な講師
初級者を脱し、中級者の時期になると、ピンインが身に付き、基本的な読み書きおよび簡単な会話が出来るようになっているはずです。
つまり、あまりにも基本的な部分よりも、より実用的な能力を身に付けたい時期だと言えます。
この場合、入門者の時のように、懇切丁寧な「至れり尽くせり」のレッスンを受けてしまうと、実際の現場に出るとあまりの違いに戸惑ってしまうことになりかねません。
そこで学習の効果を高めるために、あえて講師経験を問わず、実際のスピードで会話ができる講師を選んで「現地シミュレーション」をしてみるのも一つの方法だと思います。
さらに上級者の段階に差し掛かっている場合、迷わず「日本語不可」の講師を選んでみると良いでしょう。うまく伝わらなくても「逃げ場のない」状況に自分自身を追い込むことによって確実に即戦力が養われてくるはずです。
資格・検定対策に最適な講師
HSK、中検等の資格取得を目的にしている場合、これらの検定の出題傾向や形式が分かっていない講師を選んでしまうと、目的を達するのが難しくなるかも知れません。
ここは費用が少しかかったとしても、資格取得の指導経験があり、参考書や過去問を持っている講師を選ぶのが賢明でしょう。
ただし、受験者数の少ない検定試験、たとえば「TECC」や「通訳案内士」といった試験の場合、そもそも情報が少なく、これらに関する対策を期待できる講師は非常に少ないと思われます。
また「中検」も日本独自の試験なので、ネイティブの講師にとってあまり馴染みがなく、この方面の傾向・対策を期待するのも難しいでしょう。
こうした場合は、あくまでも受講者自身が試験対策をし、そのためのサポートを講師に求めることになると思います。
また、試験もグレードが高くなるにつれ、出題文章もより専門的になり、表現も高度になります。こういった文章をきちんと解釈できるような、基礎教養・一般常識を持っている講師が最も適切でしょう。
学習がビジネス目的の場合
ここはハッキリ言えます。
学生講師は避けましょう。
ビジネス用語の使い回しはもちろんですが、実際の社会で必要とされるビジネスマナーや商習慣について、学生の講師に期待する方が無理があると思います。
年齢について言えば、最低でも20代後半、出来れば30代以上の講師で、ビジネス経験のある講師を選ぶべきです。
このレベルになると、該当する講師がなかなか見付からないこともありうるので、自分で探すよりもスクール事務局に相談する方が早いはずです。
その際、自身の業界なども伝えておけば、ある程度の知見を持った講師を紹介してくれるかも知れません。
まとめ
オンラインスクールの場合、講師を見つけるのが最初の難関だと言えます。
しかし、一度見つかってしまえば、あとはひたすら講師を信じて進めていけば良いので、学習に集中することができ、効果を上げることができるはずです。
そしてまた、続けているうちに学習の方向や意欲が途中で変わってしまうなんてことも良くあることです。
こう言う場合は、一時的に休んでみたり、講師を変えてみるのも、学習が長続きできる秘訣なのではないかと思います。
オンラインの場合、あまり特定の講師に固執する必要もないのではないでしょうか?
ぜひ、オンラインのメリットを活かし、柔軟な学習計画を立て、無理なく続けていきましょう。
こちらも併せてお読みください